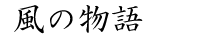現在:ある休日
俺の朝は一杯のコーヒーから始まる。
チュンチュンと小鳥のさえずる声が聞こえる。森の木々のざわめき、のどかな日の光。
春の朝は好きだ。夏のように日差しが強く暑くなっていったり冬のように布団と戯れることもない。
俺はいつものように一杯のコーヒーを淹れる。何と言ってもコーヒーは命の水だ。柔らかな笑みを見せ、コーヒーを一口含む。その時だった。
「「ふーちゃーん!あーそーぼー!!!!」」
「―!!!!」
急に目の前にひょっこりと2人の青年がわざわざ変な顔を見せながら現れる。唐突な来訪に彼はコーヒーを噴き出す。
「にゃーきたなーい!」
「にゃっ、汚いぞフーちゃん!」
その噴き出したコーヒーは目の前の2人に。汚いと文句を言われる。目の前に現れるのが悪い。しかしどこから現れたのだろうか。
まず扉を確認する。昨晩厳重に鍵を閉めたはずだ。その通り開いた形跡はない。次に窓に視線を向ける。まだ開けていない事を確認した。
「どこから来たんですか………」
「えーそれ聞いちゃうの?」
「秘密だぞー」
「「にゃー」」
変な口癖を持っているこの2人のニックネームはナイアとラト。なぜか俺を気に入っているらしく、気が付いたらいつも俺のいる所に入り浸っている。別にいるのは構わないが贔屓と見られたくないので他人の前では現れるなと言うのが本音だ。
「仕事はどうしたんです?」
「俺たちに朝からしかも休日に仕事をさせるとな!?」
「ひどいぞフーちゃん!」
「だからフーちゃん言わないでください!他の生徒が言いだしたらどうするんですか!!」
事実を言おう。俺の朝はうるさい2人の来訪者をつまみ出すところから始まる。休日なのになんて最悪な始まりなんだ、ため息をつく。
しかし休みとはいえ寝続けたり遊び呆けることはしない。誰もいない校舎を歩き、研究室へ向かう。
「俺もいるにゃ!」
「にゃー」
誰もいないのだ。誰もいないあと人の心読むなと心の中で唱え続ける。しかしまったく触れないというのは後が怖い。
「トート学長、デュマ副学長何が御用ですか?」
「あー! フーちゃんあっさり言いやがったー! なーちゃんって呼んでっていつも言ってるじゃん!」
「これは秘密の予定だぞ! らっちと呼べよ!」
そう、彼らは本当はこの学園の偉い人だ。そのくせに平教師である自分の所に入り浸っている。
それを知っている人間は少なく、今の2人は神出鬼没の謎の人物というのでこの学園内で通っている。何せ学長副学長としているときの彼らはまったくの別人なのだから。俺も疑っているのだが、理事長に確認した所「現実から目を背けるな」と言われたため事実なのだろう。頭が痛い。
そして2人は名前を呼んだ途端にどこかへ飛んで行ってしまった。
彼は本日二度目のため息をつき、研究室へ向かった。
化学研究室に到着する。ここは俺の学内の拠点のようなものだ。
本来は禁煙である校内だがここは俺の城。煙草に火をつけ、持ち込み禁止だがまた同じく俺の城なので問題はない。コーヒーを飲むために湯を沸かす。次に引き出しを開き書類を取り出し、目を通す。
その後沈黙が流れる。何やら違和感を感じ周囲を見回してしまう。
何もいない。違和感の正体はさっきまで執拗に現れていた2人が来ていないという事だった。
寂しいとか来ないことに対して残念、というわけではない。「平和なことはいいことだ」そうボソリと呟き、再び書類へ目を向ける。
あの後赤髪の少女、リリアが2人を連れてやって来た。
彼女の用事はただ単にいつもの手紙を書いてきたから持って来ただけだ。それが何か面白そうな予感がするとか変なこと考えたらしく一緒に来たのだ。
本当は少女が手紙を持ってきている事は隠したかった。しかしいつか彼らにバレることだ。潔く無視することにする。そして少女がいなくなったことを確認し、手紙を開ける。
「あー!リリちゃんの渾身のお手紙ー!」
「開けるのはしつれーだろ!」
残っていた2人はそれぞれぶーぶーとたれる。
「というか!校則違反!外部との連絡を上の許可無しに行わないで!」
「罰則!罰則!」
こううるさくなるから人に、とくにこの2人には言いたくなかったんだと彼は心の中で叫ぶ。コイツらは偉い人だ? そうだったな。忘れていた。
「いや一言も外の奴とは言ってないだろう。自分がそんな規則を違反するようなことはしない、です」
「校内所定の場所以外では禁煙」
「学内で勝手にコーヒー作って飲むなよ!」
「うぐ」
即言葉が詰まる。これ以上何か言う事は余計な失言を招くだろう。そっぽを向き手紙を開く。
手紙を見つめ、少し笑みを浮かべてしまう。2人がそれを覗こうとするとその手紙を閉じた。
「でもリリアちゃんが頑張って書いた手紙を勝手に開けるのはひどいよ?」
「かわいそうだぞ」
「あのなあ………」
首をガクッと落とす。わざと言っているのかそれとも本当に疑問を持っているのかは2人の表情では感じ取ることができない。この2人は何を考えているのか本当に分からない。
「あまり余計なことを書かれていたら困る。何か変なことが彼女に起こってないか確認。検閲してるだけです。自分は彼女の担当教師なので」
担当教師、それは主に孤児の親代わりになる教師。俺はそのリリアの担当であり、大暴れの片付け係にもなっている。
他の教師達には一種の罰ゲームだと哀れに思われているようだが、そこに対してはあまり気にしていない。リリアはまだ扱いやすい。
「うーん、まあ確かに悩みとかあったらの確認ついでに街の人に手紙を送れればいいか。フーちゃん考えてるなー」
「フーちゃんにしては理にかなってるなー」
「フーちゃん言うなと何度言えばいいんですかあなた方は!」
「「キャー!」」
ついつい怒鳴ってしまった。その声で2人は蜘蛛の子を散らすように部屋から出ていった。俺は多分本日一番の大きなため息をつき、手紙を再び開いた。
それはとても可愛らしい字でそれは書かれていた。途中から色々面倒になったのか誤魔化したりしてる様に思わず笑みがこぼれてしまう。
彼は引き出しから真っ白な便箋とペンを取り出し、空を見上げる。
「アンナ、この子は楽しくやってるぞ」
ポツリと1人呟く。部屋の外ではこっそり2人が笑みを見せていた。
リリア
元気です。高等部進学おめでとう。行けたみたいで安心した。新しい友達もできたのならよかった。
お前がそれを楽しいと思い、自分であることを示せるならば、自由にしたらいい。
しかしほどほどにしておくんだな。
父の事はそんなに気にせずいっぱい遊べばいい。手紙ありがとう。きっと母さんも喜んでいる。
仕事がひと段落したら会いに行けるから気長に待ってほしい。
いつも待たせてばかりでごめんな。父より
最終更新:2023/02/02