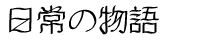不思議な出会い
「こんにちは」
「こ、こんにちは……?」
赤髪の少女は森の中。ここで出会ったのは桔梗色の不思議な雰囲気を放つ女性。この出会いは数刻前までさかのぼる。
「あれ迷った?」
リリアは周りをキョロキョロと見回す。今日は学園を囲む森の探索。自分の持ち味はイタズラだけではない。探索する好奇心も大事であると拳を振り上げたのが2時間前の自室。
旧校舎で幽霊に出会いフウガに怒られ課題まみれになってから解放されるまで1週間はかかっていた。しばらくは学園内で走り回ることさえも許されず、ストレスがたまっていた彼女は「学園内がダメならセンセの目がない外で遊べばいいじゃない!」と思い立ち、シェリーからもらった弁当を持って寮を飛び出した。
街の人に挨拶して回り、本日のメインイベントが始まる。にぎやかな街を過ぎるとそこは人の気配を感じられない草木が覆い茂る森の中。
しばらく進んでみると全く変わらない緑色の景色。ウロウロと歩き回っている内にどこから来たのか、戻ってきているかも分からない。つまり迷子である。
「うー……いや好奇心たっぷりの探検家は迷子なんかで狼狽えない! ちょっつもーしんー!」
昨日銀髪の教師から教えてもらった言葉を思い出しながらまっすぐ進む。
「うえええリンーレイーサナーセンセー!!」
さらに数刻後涙目で少女は森の中で叫んでいた。その場に伏せようと思ったがここで止まったら負けだと考えたのか我慢しとぼとぼと歩きだす。自分の歩く音だけが響く。せめてリンだけでも誘えばよかったと後悔しても迷子になった後ではもう遅い。考えることをあきらめようとした時だった。
「歌……?」
何やら歌声が聞こえる。どうやらその声の主は女性のようだ。迷い子となっている少女はその声に誘われるように森の奥へと進んでいくのだった。
少し森を進むと開けた場所にたどり着く。その中心の石の上に女性が座り歌を唄っていた。桔梗色の長い髪を靡かせた女性は気配を感じたのか歌を止め赤い目を開きリリアに笑顔を見せる。
「こんにちは」
「こ、こんにちは……?」
上品な印象。リリアより一回り年は上だろうか。一瞬見とれてしまう。しかしすぐに気を取り直し、その女性に質問をする。
「あの、街に戻るにはどちらの方に行けばいいのです?」
「あちら」
女性は石畳の道を指さす。自分が来た道と違い、一定の整備はされているようだ。
「あなた、お名前は?」
女性はクスクスと笑う。少女もつられて笑いながら
「リリアです、の。お姉さんは?」
「私はセイラ。よろしくお願いしますね、リリアさん」
女性の自己紹介をぼんやりと聞きながらじっと観察する。自分と同じ高等部の先輩だろうか。しかしこれほどまでに綺麗な人がいたら常に話題になっているだろう。例えば新聞部が突撃して記事になったりしているはず。という事は教師だろうか。雰囲気的に国語や音楽関係だったら納得できそうだ。帰ったら銀髪の教師に聞いてみよう。
「あの、リリアさん」
「え? あ、はい! ウチは元気です! じゃなかった。えっと」
「早くしないと夕方になって先生にまた怒られてしまいますよ?」
「あー! もうこんな時間なの!?」
少女はポシェットに入れていた時計を見るともう4時。きっとリンもレイも心配しているだろう。
女性に示されて道の方に足を進める。
「セーラさんありがとございますなの!」
「構わないのよ。フウガによろしくって伝えておいてちょうだい?」
「はい! えっと、また会えますか?」
「多分会えると思いますわよ? 授業が休みの日はここにいますわ」
「じゃあ次はお菓子とか持ってくるの!」
「そう。じゃあ守り神様から加護のあらんことを」
ブンブンと手を振り走って行く。整備された道に従い進んでいくと学園旧校舎の裏に辿り着く。
「ここに繋がってたんだ……。ってあれ? セーラさんにセンセの事言ってたっけ?」
うーんと首を傾げるが生憎少女は長い事考える行為は苦手である。すぐにニィと笑い腕を振り上げた。
「ま、いっか。また会いに行ったとき聞いてみよ!」
寮に帰った後、寮の前で待っていたレイとリンに心配したのよと日が傾くまで怒られてしまった。
その後リリアは昼に会った女性について話すことにする。
「セーラって先生いたっけ?」
「セーラ……ってもしかして」
「リリ、お前は少し学園に興味持つ方がいい」
「?」
首を傾げていると2人はため息を吐いた。
「セイラ理事長よ。この学園で一番偉い先生」
「……学園で知らない人間はいないと思ってたんだが……」
「え、ええええ!?」
本日一番の驚きの声が寮前で響き渡った。
「あの子がリリア・サリス。アレがフウガに必要な娘だったの……?」
残された桔梗色の女性はボソリと呟いた。先程までの柔らかな笑みは消え、石畳の道を睨み付けていた。
「まあいいわ。おかしな部分は無さそうだったし放置で問題ないでしょう」
女性の周辺につむじ風が吹き荒れる。風が収まるとそこは何もなかったかのように静まる森であった。
最終加筆修正:2021/09/24